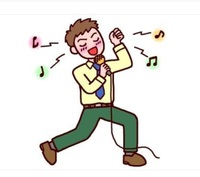よう言わんわ
Posted by Even侍 at 12:33 2013年09月29日
「よう言わんわ」。大阪弁で、「あきれてものが言えない」・・といった状況で使われる言葉ですね。
※ニュアンス的には、「どうしようもないな」「どうしろっていうんだ」「あきれてものがいえないな」「開いた口がふさがらないぜ」「かなわんな」「まいったな」「あきらめました」「私の負けです」などなど、シチュエーションに応じて複雑微妙に意味合いが変化していく(出典:大阪弁完全マスター講座)。
この言葉、亡くなった私の祖母がよく使っていた言葉で、物心ついたころからしょっちゅう聞かされていたため、自分の言語や思考回路のベースの部分に刷り込まれているような気がします。私自身は生まれも育ちも南九州ですが、祖父は大阪、祖母も生まれは違うものの、少女時代から成年まで大阪で過ごしたようで、言葉はほぼ大阪弁だったと思います。ですので、「おおきに」とか、「えらいなー(大変だとか、疲れたの意)」という言葉は、我が家では普通に使われていて、地元の言葉ももちろん使うわけで、まったく違和感なくそれらの言葉が混ざって使われていました。そのせいか、テレビで関西の芸能人や漫才師がしゃべっているのを聞いても、ほとんど違和感を感じることはありませんでしたし、どこか親近感を持って耳にしていたようにも思います。子供のころは、東京の親戚やその子供たちの言葉の方が、(意味はもちろん分かるのですが)異国の言葉のように聞こえたのをよく覚えています。

そういえば、小さい頃祖母とお風呂に入ると、よく「背中をこすって(洗って)くれ」といわれ、普通にタオルでこすると「全然、力が入っとらん。」といつも言われてました。で、小学校2年生くらいだったでしょうか。久しぶりに祖母と風呂に入ったとき、また「力が足らん」といわれたので、その頃、剣道に通っていて多少体力に自信がついてきていた私は「よおし!」と気合をいれ、渾身の力を両手に込めて、タオルで祖母の背中を目いっぱいこすりました。そしたら、祖母が飛び上がって「痛いがな!!」と叫んだため、こっちもびっくりして飛び上がりました。同時に、その祖母の反応がドリフのコントみたいで、可笑しくなって吹き出しながら、「だって、ばあちゃんが”力が足らん”って言ったやろ!」とか言い返したのを覚えています。あの、「痛いがな!」という声が、今も耳に残っています。
で、「よう言わんわ」ですが、社会人になって始めて大阪に出張し、お客さんと4人で食事をしながら雑談していたときのこと。その場におられたのは、2人は大阪出身で、1人は大阪で何十年も暮らしている方だったと記憶しています。私は、自分の祖父母の話をしながら、「大阪弁で”よう言わんわ”って言いますか?」と聞きました。そしたら、その場にいた全員が、「よう言わんわ?使うかなー。」「うーん、聞いたことはあるような気もするけど、普通に使うかなー。」との意外な反応。ずっと大阪弁だと信じていた私は、「ええー?そうなんだ。じゃあ、あの”よう言わんわ”は、ばあちゃんの造語やったのか?」と、急に自信が無くなり、「ああ、そうなんですね。」とその場はそれで終わりました。
それからしばらくは仕事で関西に行っても大阪弁の話はしなくなったのですが、その2年後くらい、家でテレビを見ていたら昔の歌謡曲を特集しており、その中で笠置シヅ子という歌手の「買物ブギ」という曲の中で、「わてほんまによういわんわ、わてほんまによういわんわ」と連呼しているではありませんか。この曲を聴いたのはそのときが初めてでしたが、「おおー!これや!やっぱ、あったやんけー!」と、さすがにここまでは普段使わない関西弁もどき?を声に出して、テレビの前で叫びました。同時に、「じゃあ、あのときのお客さんたち、何だったんだろう?」と不思議に感じました。別に意地悪で知らないふりしているようでもなかったですし(そんなことしても意味ないし)、たぶん、同じ大阪でもあまり使われない地区で育ったのかなあ...。と、今は付き合いの無くなったその方々との一件は、今も謎のままです。まあ、九州だって同じ南九州でも全然言葉が違いますし、たいしたことではないですが。
いやー、方言って難しいもんですね。あ、オチないわ(笑)。
※ニュアンス的には、「どうしようもないな」「どうしろっていうんだ」「あきれてものがいえないな」「開いた口がふさがらないぜ」「かなわんな」「まいったな」「あきらめました」「私の負けです」などなど、シチュエーションに応じて複雑微妙に意味合いが変化していく(出典:大阪弁完全マスター講座)。
この言葉、亡くなった私の祖母がよく使っていた言葉で、物心ついたころからしょっちゅう聞かされていたため、自分の言語や思考回路のベースの部分に刷り込まれているような気がします。私自身は生まれも育ちも南九州ですが、祖父は大阪、祖母も生まれは違うものの、少女時代から成年まで大阪で過ごしたようで、言葉はほぼ大阪弁だったと思います。ですので、「おおきに」とか、「えらいなー(大変だとか、疲れたの意)」という言葉は、我が家では普通に使われていて、地元の言葉ももちろん使うわけで、まったく違和感なくそれらの言葉が混ざって使われていました。そのせいか、テレビで関西の芸能人や漫才師がしゃべっているのを聞いても、ほとんど違和感を感じることはありませんでしたし、どこか親近感を持って耳にしていたようにも思います。子供のころは、東京の親戚やその子供たちの言葉の方が、(意味はもちろん分かるのですが)異国の言葉のように聞こえたのをよく覚えています。

そういえば、小さい頃祖母とお風呂に入ると、よく「背中をこすって(洗って)くれ」といわれ、普通にタオルでこすると「全然、力が入っとらん。」といつも言われてました。で、小学校2年生くらいだったでしょうか。久しぶりに祖母と風呂に入ったとき、また「力が足らん」といわれたので、その頃、剣道に通っていて多少体力に自信がついてきていた私は「よおし!」と気合をいれ、渾身の力を両手に込めて、タオルで祖母の背中を目いっぱいこすりました。そしたら、祖母が飛び上がって「痛いがな!!」と叫んだため、こっちもびっくりして飛び上がりました。同時に、その祖母の反応がドリフのコントみたいで、可笑しくなって吹き出しながら、「だって、ばあちゃんが”力が足らん”って言ったやろ!」とか言い返したのを覚えています。あの、「痛いがな!」という声が、今も耳に残っています。
で、「よう言わんわ」ですが、社会人になって始めて大阪に出張し、お客さんと4人で食事をしながら雑談していたときのこと。その場におられたのは、2人は大阪出身で、1人は大阪で何十年も暮らしている方だったと記憶しています。私は、自分の祖父母の話をしながら、「大阪弁で”よう言わんわ”って言いますか?」と聞きました。そしたら、その場にいた全員が、「よう言わんわ?使うかなー。」「うーん、聞いたことはあるような気もするけど、普通に使うかなー。」との意外な反応。ずっと大阪弁だと信じていた私は、「ええー?そうなんだ。じゃあ、あの”よう言わんわ”は、ばあちゃんの造語やったのか?」と、急に自信が無くなり、「ああ、そうなんですね。」とその場はそれで終わりました。
それからしばらくは仕事で関西に行っても大阪弁の話はしなくなったのですが、その2年後くらい、家でテレビを見ていたら昔の歌謡曲を特集しており、その中で笠置シヅ子という歌手の「買物ブギ」という曲の中で、「わてほんまによういわんわ、わてほんまによういわんわ」と連呼しているではありませんか。この曲を聴いたのはそのときが初めてでしたが、「おおー!これや!やっぱ、あったやんけー!」と、さすがにここまでは普段使わない関西弁もどき?を声に出して、テレビの前で叫びました。同時に、「じゃあ、あのときのお客さんたち、何だったんだろう?」と不思議に感じました。別に意地悪で知らないふりしているようでもなかったですし(そんなことしても意味ないし)、たぶん、同じ大阪でもあまり使われない地区で育ったのかなあ...。と、今は付き合いの無くなったその方々との一件は、今も謎のままです。まあ、九州だって同じ南九州でも全然言葉が違いますし、たいしたことではないですが。
いやー、方言って難しいもんですね。あ、オチないわ(笑)。