中年の主張
Posted by Even侍 at 23:27 2013年12月19日
「私の言い分」なんて意味を込めて始めたブログですが、いざやってみると、そんなに世間様に向かって声高に言いたいことってないもんだ・・・ということに気づきました。と、いきなりブログを長期ほったらかしにしたことへの言い訳からはじめましたが(笑)、いや、これは結構自分にとっても「へー。」と気づかされることだったんです。
私は普段から、自分の意見やアイデア、ときには批判も含めて自分の考えを他者に伝えたい・・という欲求が強い方だと思います。朝起きて夜寝るまでのあらゆる瞬間瞬間に、「こうすべきかな? こうあるべき? こうした方が面白いんじゃ? それは良くないことでは?」みたいなことを考えている気がしますし、また実際に言葉として口にすることも多いです。もちろん、日本人的な「和を尊ぶ」精神の大切さもわかってはいるつもりなので、あまり「俺が、俺が。」みたいな態度を取るのは好きではないのですが、精一杯セーブしているつもりでも、やはり人前で意見をはっきり口にしたり、相手に投げかけたりしていると、それを快く受け止めない人もいて、ちょっとした衝突や摩擦につながることもあります(なんか、文章で書くと、やたら喧嘩っ早いように感じられるかもしれませんが、そんなことはないですよ。^-^;)。
この”摩擦”は、傾向としては職場で起こる確率が高く、また年長者との間で起こる確率が高いように思います。自分自身もそう若くはないですが、二十歳ぐらいのときからずっと同じようなことを感じてきて、統計を取ったわけではないですが、自分の中ではこれはほぼ「実証」されています。
そもそも日本語において、「自己主張」という言葉自体、ネガティブなニュアンスで 語られることが多いですよね。「あの人は自己主張が強い人だ。」というのを、ほめ言葉と捉える人はあまりいないでしょうね。日本語のイメージだと、「我が強く、自己中心的な人」という意味合いが多少なりとも込められているように思います。
語られることが多いですよね。「あの人は自己主張が強い人だ。」というのを、ほめ言葉と捉える人はあまりいないでしょうね。日本語のイメージだと、「我が強く、自己中心的な人」という意味合いが多少なりとも込められているように思います。
けど、ほんとにそうなんでしょうか。自分の意見や主張を封じ込めて生きていくのって、あまり健全じゃないように思うんですけどね。「自己主張=エゴ」・・これはあまりにも乱暴ですし、短絡的だと思います。人の価値観はさまざまですし、何が「正しい」ってことはなく、主義主張がかみ合わない、あるいは相反することもあることは当然だと思います。ですが、かみ合わないがゆえに起こりうる衝突や摩擦を徹底して回避し、自分(または自分たち)が信じる意見を明確にしない・・というのは、やはり私にはどうにも性に合いません。ある程度は大人として、社会人としての「節度」的な部分で、自分の考えと感情を抑えて他人の意見に耳を傾けつつも、ここぞというときには、やはり思いを口にすべきではないかと思います。
と、昔からこんな感じだったので、ブログなるものが流行り始めたころから、「おおー、これは俺やったら、かなーり言いたいことありそうやし、ネタには困らんかも。」なんて思ってました。とはいいつつ、始めるまでずいぶん時間がかかり、ようやく開始したこのブログも、更新頻度はこんなものです。^-^;
で、冒頭に書きました私なりの「気づき」なんですが、結局、私の意見や主張というのは、別に世間一般にうったえたいような高尚なものでも政治的なものでもなく、普段の生活や仕事、人間関係、いわゆる「利害関係」の中でこそ発したい種類のものだったかも・・ってことです。(あ、ちなみにこの「利害」は経済的な意味ではありません。)
日々、人と接し、(広い意味で)ともに仕事をする中でこそ、「こうしたい、こうありたい」という理想のようなものが自分の中から湧き出てきて、それこそが「意見」や「主張」の源泉であり、原動力なんだろうな・・と、この「ブログサボり」を通じて分かったような気がします。当たり前のことなんでしょうが、やっぱり人間、日々のよしなしごとが一番大事であって、そこで泣いたり笑ったり怒ったり喜んだりってことが一番価値があるんでしょうね。じゃあ、それブログに書いたら・・てご意見もありそうですが、まずは現実の中で勝負して、消化していこうかなと。たまにはネットでちょっとばかし「中年の主張」もさせていただくかもしれませんが。^^
けどほんとあれですよね。「理想」だの「主張」だのって、日常的に聴かされる相手は、やっぱり疲れるんだろうなあ・・と、反省することも多々あります。私と接していただく皆さんには大変恐縮ですが、うざいやつとお思いかもしれませんが、たまーには、ほんの少しばかりあっしの言い分も聞いておくんなさい。・・とお願いして、今日はこれまで。m(_ _)m
私は普段から、自分の意見やアイデア、ときには批判も含めて自分の考えを他者に伝えたい・・という欲求が強い方だと思います。朝起きて夜寝るまでのあらゆる瞬間瞬間に、「こうすべきかな? こうあるべき? こうした方が面白いんじゃ? それは良くないことでは?」みたいなことを考えている気がしますし、また実際に言葉として口にすることも多いです。もちろん、日本人的な「和を尊ぶ」精神の大切さもわかってはいるつもりなので、あまり「俺が、俺が。」みたいな態度を取るのは好きではないのですが、精一杯セーブしているつもりでも、やはり人前で意見をはっきり口にしたり、相手に投げかけたりしていると、それを快く受け止めない人もいて、ちょっとした衝突や摩擦につながることもあります(なんか、文章で書くと、やたら喧嘩っ早いように感じられるかもしれませんが、そんなことはないですよ。^-^;)。
この”摩擦”は、傾向としては職場で起こる確率が高く、また年長者との間で起こる確率が高いように思います。自分自身もそう若くはないですが、二十歳ぐらいのときからずっと同じようなことを感じてきて、統計を取ったわけではないですが、自分の中ではこれはほぼ「実証」されています。
そもそも日本語において、「自己主張」という言葉自体、ネガティブなニュアンスで
 語られることが多いですよね。「あの人は自己主張が強い人だ。」というのを、ほめ言葉と捉える人はあまりいないでしょうね。日本語のイメージだと、「我が強く、自己中心的な人」という意味合いが多少なりとも込められているように思います。
語られることが多いですよね。「あの人は自己主張が強い人だ。」というのを、ほめ言葉と捉える人はあまりいないでしょうね。日本語のイメージだと、「我が強く、自己中心的な人」という意味合いが多少なりとも込められているように思います。けど、ほんとにそうなんでしょうか。自分の意見や主張を封じ込めて生きていくのって、あまり健全じゃないように思うんですけどね。「自己主張=エゴ」・・これはあまりにも乱暴ですし、短絡的だと思います。人の価値観はさまざまですし、何が「正しい」ってことはなく、主義主張がかみ合わない、あるいは相反することもあることは当然だと思います。ですが、かみ合わないがゆえに起こりうる衝突や摩擦を徹底して回避し、自分(または自分たち)が信じる意見を明確にしない・・というのは、やはり私にはどうにも性に合いません。ある程度は大人として、社会人としての「節度」的な部分で、自分の考えと感情を抑えて他人の意見に耳を傾けつつも、ここぞというときには、やはり思いを口にすべきではないかと思います。
と、昔からこんな感じだったので、ブログなるものが流行り始めたころから、「おおー、これは俺やったら、かなーり言いたいことありそうやし、ネタには困らんかも。」なんて思ってました。とはいいつつ、始めるまでずいぶん時間がかかり、ようやく開始したこのブログも、更新頻度はこんなものです。^-^;
で、冒頭に書きました私なりの「気づき」なんですが、結局、私の意見や主張というのは、別に世間一般にうったえたいような高尚なものでも政治的なものでもなく、普段の生活や仕事、人間関係、いわゆる「利害関係」の中でこそ発したい種類のものだったかも・・ってことです。(あ、ちなみにこの「利害」は経済的な意味ではありません。)
日々、人と接し、(広い意味で)ともに仕事をする中でこそ、「こうしたい、こうありたい」という理想のようなものが自分の中から湧き出てきて、それこそが「意見」や「主張」の源泉であり、原動力なんだろうな・・と、この「ブログサボり」を通じて分かったような気がします。当たり前のことなんでしょうが、やっぱり人間、日々のよしなしごとが一番大事であって、そこで泣いたり笑ったり怒ったり喜んだりってことが一番価値があるんでしょうね。じゃあ、それブログに書いたら・・てご意見もありそうですが、まずは現実の中で勝負して、消化していこうかなと。たまにはネットでちょっとばかし「中年の主張」もさせていただくかもしれませんが。^^
けどほんとあれですよね。「理想」だの「主張」だのって、日常的に聴かされる相手は、やっぱり疲れるんだろうなあ・・と、反省することも多々あります。私と接していただく皆さんには大変恐縮ですが、うざいやつとお思いかもしれませんが、たまーには、ほんの少しばかりあっしの言い分も聞いておくんなさい。・・とお願いして、今日はこれまで。m(_ _)m
よう言わんわ
Posted by Even侍 at 12:33 2013年09月29日
「よう言わんわ」。大阪弁で、「あきれてものが言えない」・・といった状況で使われる言葉ですね。
※ニュアンス的には、「どうしようもないな」「どうしろっていうんだ」「あきれてものがいえないな」「開いた口がふさがらないぜ」「かなわんな」「まいったな」「あきらめました」「私の負けです」などなど、シチュエーションに応じて複雑微妙に意味合いが変化していく(出典:大阪弁完全マスター講座)。
この言葉、亡くなった私の祖母がよく使っていた言葉で、物心ついたころからしょっちゅう聞かされていたため、自分の言語や思考回路のベースの部分に刷り込まれているような気がします。私自身は生まれも育ちも南九州ですが、祖父は大阪、祖母も生まれは違うものの、少女時代から成年まで大阪で過ごしたようで、言葉はほぼ大阪弁だったと思います。ですので、「おおきに」とか、「えらいなー(大変だとか、疲れたの意)」という言葉は、我が家では普通に使われていて、地元の言葉ももちろん使うわけで、まったく違和感なくそれらの言葉が混ざって使われていました。そのせいか、テレビで関西の芸能人や漫才師がしゃべっているのを聞いても、ほとんど違和感を感じることはありませんでしたし、どこか親近感を持って耳にしていたようにも思います。子供のころは、東京の親戚やその子供たちの言葉の方が、(意味はもちろん分かるのですが)異国の言葉のように聞こえたのをよく覚えています。

そういえば、小さい頃祖母とお風呂に入ると、よく「背中をこすって(洗って)くれ」といわれ、普通にタオルでこすると「全然、力が入っとらん。」といつも言われてました。で、小学校2年生くらいだったでしょうか。久しぶりに祖母と風呂に入ったとき、また「力が足らん」といわれたので、その頃、剣道に通っていて多少体力に自信がついてきていた私は「よおし!」と気合をいれ、渾身の力を両手に込めて、タオルで祖母の背中を目いっぱいこすりました。そしたら、祖母が飛び上がって「痛いがな!!」と叫んだため、こっちもびっくりして飛び上がりました。同時に、その祖母の反応がドリフのコントみたいで、可笑しくなって吹き出しながら、「だって、ばあちゃんが”力が足らん”って言ったやろ!」とか言い返したのを覚えています。あの、「痛いがな!」という声が、今も耳に残っています。
で、「よう言わんわ」ですが、社会人になって始めて大阪に出張し、お客さんと4人で食事をしながら雑談していたときのこと。その場におられたのは、2人は大阪出身で、1人は大阪で何十年も暮らしている方だったと記憶しています。私は、自分の祖父母の話をしながら、「大阪弁で”よう言わんわ”って言いますか?」と聞きました。そしたら、その場にいた全員が、「よう言わんわ?使うかなー。」「うーん、聞いたことはあるような気もするけど、普通に使うかなー。」との意外な反応。ずっと大阪弁だと信じていた私は、「ええー?そうなんだ。じゃあ、あの”よう言わんわ”は、ばあちゃんの造語やったのか?」と、急に自信が無くなり、「ああ、そうなんですね。」とその場はそれで終わりました。
それからしばらくは仕事で関西に行っても大阪弁の話はしなくなったのですが、その2年後くらい、家でテレビを見ていたら昔の歌謡曲を特集しており、その中で笠置シヅ子という歌手の「買物ブギ」という曲の中で、「わてほんまによういわんわ、わてほんまによういわんわ」と連呼しているではありませんか。この曲を聴いたのはそのときが初めてでしたが、「おおー!これや!やっぱ、あったやんけー!」と、さすがにここまでは普段使わない関西弁もどき?を声に出して、テレビの前で叫びました。同時に、「じゃあ、あのときのお客さんたち、何だったんだろう?」と不思議に感じました。別に意地悪で知らないふりしているようでもなかったですし(そんなことしても意味ないし)、たぶん、同じ大阪でもあまり使われない地区で育ったのかなあ...。と、今は付き合いの無くなったその方々との一件は、今も謎のままです。まあ、九州だって同じ南九州でも全然言葉が違いますし、たいしたことではないですが。
いやー、方言って難しいもんですね。あ、オチないわ(笑)。
※ニュアンス的には、「どうしようもないな」「どうしろっていうんだ」「あきれてものがいえないな」「開いた口がふさがらないぜ」「かなわんな」「まいったな」「あきらめました」「私の負けです」などなど、シチュエーションに応じて複雑微妙に意味合いが変化していく(出典:大阪弁完全マスター講座)。
この言葉、亡くなった私の祖母がよく使っていた言葉で、物心ついたころからしょっちゅう聞かされていたため、自分の言語や思考回路のベースの部分に刷り込まれているような気がします。私自身は生まれも育ちも南九州ですが、祖父は大阪、祖母も生まれは違うものの、少女時代から成年まで大阪で過ごしたようで、言葉はほぼ大阪弁だったと思います。ですので、「おおきに」とか、「えらいなー(大変だとか、疲れたの意)」という言葉は、我が家では普通に使われていて、地元の言葉ももちろん使うわけで、まったく違和感なくそれらの言葉が混ざって使われていました。そのせいか、テレビで関西の芸能人や漫才師がしゃべっているのを聞いても、ほとんど違和感を感じることはありませんでしたし、どこか親近感を持って耳にしていたようにも思います。子供のころは、東京の親戚やその子供たちの言葉の方が、(意味はもちろん分かるのですが)異国の言葉のように聞こえたのをよく覚えています。

そういえば、小さい頃祖母とお風呂に入ると、よく「背中をこすって(洗って)くれ」といわれ、普通にタオルでこすると「全然、力が入っとらん。」といつも言われてました。で、小学校2年生くらいだったでしょうか。久しぶりに祖母と風呂に入ったとき、また「力が足らん」といわれたので、その頃、剣道に通っていて多少体力に自信がついてきていた私は「よおし!」と気合をいれ、渾身の力を両手に込めて、タオルで祖母の背中を目いっぱいこすりました。そしたら、祖母が飛び上がって「痛いがな!!」と叫んだため、こっちもびっくりして飛び上がりました。同時に、その祖母の反応がドリフのコントみたいで、可笑しくなって吹き出しながら、「だって、ばあちゃんが”力が足らん”って言ったやろ!」とか言い返したのを覚えています。あの、「痛いがな!」という声が、今も耳に残っています。
で、「よう言わんわ」ですが、社会人になって始めて大阪に出張し、お客さんと4人で食事をしながら雑談していたときのこと。その場におられたのは、2人は大阪出身で、1人は大阪で何十年も暮らしている方だったと記憶しています。私は、自分の祖父母の話をしながら、「大阪弁で”よう言わんわ”って言いますか?」と聞きました。そしたら、その場にいた全員が、「よう言わんわ?使うかなー。」「うーん、聞いたことはあるような気もするけど、普通に使うかなー。」との意外な反応。ずっと大阪弁だと信じていた私は、「ええー?そうなんだ。じゃあ、あの”よう言わんわ”は、ばあちゃんの造語やったのか?」と、急に自信が無くなり、「ああ、そうなんですね。」とその場はそれで終わりました。
それからしばらくは仕事で関西に行っても大阪弁の話はしなくなったのですが、その2年後くらい、家でテレビを見ていたら昔の歌謡曲を特集しており、その中で笠置シヅ子という歌手の「買物ブギ」という曲の中で、「わてほんまによういわんわ、わてほんまによういわんわ」と連呼しているではありませんか。この曲を聴いたのはそのときが初めてでしたが、「おおー!これや!やっぱ、あったやんけー!」と、さすがにここまでは普段使わない関西弁もどき?を声に出して、テレビの前で叫びました。同時に、「じゃあ、あのときのお客さんたち、何だったんだろう?」と不思議に感じました。別に意地悪で知らないふりしているようでもなかったですし(そんなことしても意味ないし)、たぶん、同じ大阪でもあまり使われない地区で育ったのかなあ...。と、今は付き合いの無くなったその方々との一件は、今も謎のままです。まあ、九州だって同じ南九州でも全然言葉が違いますし、たいしたことではないですが。
いやー、方言って難しいもんですね。あ、オチないわ(笑)。
「時間厳守」とは?
Posted by Even侍 at 22:35 2013年08月07日
○「時間厳守」=「5分前行動」?
始業時刻や終業時刻、ミーティングの開始時刻、顧客へのアポイント時刻、来客の予定時刻など、仕事においては、いつも「定刻」がつきまといます。仕事に限らず、起床時刻や登校時間、PTAの会合時間、デートの待ち合わせ時間など、普通の人なら、時間(時刻)をある程度守って生きているはずです。そして、その時刻には原則、「遅れないこと」が求められます。「時間に遅れても、全然平気でノープロブレム」という人は、大物の外タレでもないかぎ り、平穏には生きていけないでしょう。
り、平穏には生きていけないでしょう。
そうなると、決まった時刻に、努力して「遅れない」ようにする・・というのが、普通の人の感覚であり、ましてや仕事であれば、当然のこととして遅れない工夫を多くの人がされているかと思います。具体策としては、「定刻よりも少し前に現地に着く、待機する。」ということが一般的でしょう。よく言われるのが、「5分前行動」などの言葉です。なかには、自分の時計をわざと5分早めている人もいます。5分どころか、20分も30分も前に入る人もいます。なるほど、これを実行すれば、定刻に「遅れる」ことはなくなります。約束の時間に遅れて、待たせた人(達)に文句を言われることもなくなるわけです。
では、これが、「時間厳守」の特効薬であり、これが時間管理の極意なのでしょうか。
たしかに、「時間より早め」は、「定刻に居る」ことには有効であり、その事自体に異論はありません。しかし、個人的には、この「早め、早め症候群」に異を唱えたくなるときがあります。一度立ち止まって、本来の時間厳守の「意味」を考えるべきだと思うのです。なぜ「時間厳守」なのか。それは、「ある約束事を、事前に決めた定刻通り始めることで効率的に時間を使い、決められた時間内で最大限の成果を上げる」・・という「目的」を達成する「手段」として、時間厳守の観念が存在していると言えないでしょうか。しかしながら、ともすると、この時間厳守や「早く着く」こと自体が無意識に「目的化」されてしまい、結果として、「早め、早め」が最も重要な目的であり、価値のあることのように勘違いされることが世の中では(とくに組織では)よくあるように思います。「早め」が目的になってしまうと、10分、20分、いや1時間でも2時間でも早く着くことが“優れた”ことのようにはき違え、そうしない人を非難する・・という、非常に奇妙な現象が起こる場合があります。その一方で、そこまでして「前倒し」して始めた仕事や会議の中身はさっぱり・・なんてこともあるように思います。
私自身は、時間に正確でありたいと思い、電波時計が発売された当初から腕時計はずっとこのタイプですが、昔、会議のきっかり3分前に会議室に入室したら、私以外は全員着座しており、上席者に「遅い!」となじられた経験があります。10数年も前の話ですが、今もってその考えは理解できませんし、承服できません。
○「定刻」とは、前でも後でもない
定刻とは、決められた時間、当事者同士が約束した時間ですよね。つまり、合意に基づいて決められた時刻の事を指します。交通機関であれば、電車やバス、飛行機やフェリーなど、すべて、「定刻」を元に動いています。 朝一便の出発時刻が「7:30」ということは、「7:30」に出発する・・ということが交通機関を運営する会社と利用者側との合意事項であり、これは、「7:00」でもなく、「7:40」でもありません。時間に正確であり、「時間厳守」というのは、この場合、「7:30」ジャストを指します。もし、電車が勝手に、「5分前行動」などといって、7:25に発車したら、利用者は怒るでしょうし、頻発すれば、大きな混乱を招き、危険ですらあります。かといって、7:40まで遅れるのも、非常に迷惑です。
私たちの身の回りではどうでしょうか。前記のように、「○時○分定刻」に対して、とかく「早め、早め」が無条件に美徳とされていないでしょうか?出社時間であれば、早く出勤すればするほど、会議であれば、早く会議室に行けば行くほど“偉い”かのような常識?があるようにも感じます。
しかし、果たして、そうでしょうか。もし、「決めた時間より早いほうが良いことがある」のであれば、一体何のために「定刻」を定めるのでしょうか。10分早いほうが絶対的にいいという根拠があるのであれば、定刻を10分早く設定し、その時間を厳守した方がいいと思います。巷で美徳とされがちな、「定刻より早め(の入室、入場、待機、あるいは開始)」とは、単に「決めた時間を、“前にずらす”」ということであり、「時間に対して不正確」といえないでしょうか。私は、7:30は、あくまで7:30が定刻であり、「早い方が偉い」というのは、根拠のない幻想だと思います。大事なのは、「7:30ジャストに、そこにいる(or行動を開始する)ことを守る。」であり、そして、「その仕事や活動の質を上げる」ことではないでしょうか。
こういうと、「時間前に、約束の場所に行くことは悪いことか」と反論される方もおられるかもしれませんが、そういう意味ではありません。私自身も、時間を守る場合は、おおむね5分前くらいには、現地にいることが多いです。その際に留意するのは、「時間を守る」ことであり、そのために事前に「どう行動するか」ということだけです。当然、「時間に遅れる」ことは、NGであり、当人のミスです。電車や飛行機と同様、遅れた人を待つ必要は全くありません。「遅れる」というミスを起こした場合は、そのリスクを自分で背負う必要があると思います。だからといって、何も考えず、必要以上に早め、早めに現地に行って、待ち時間をつくることは、時間の浪費だと思います。その時間は、多くの場合「非生産的」な時間になります。営業マンの例でいえば、あまり早く約束の時間より前に顧客を訪問することは、失礼な行為になると思います。個人的には、営業訪問の場合は、2分前くらいがちょうどよいのでは・・と思っています。
結論として申し上げたいのは、「時間厳守」、つまり「時間(定刻、定時)を守る」ということにおいて大事なのは、無策に早めに行くことではなく、「自分の采配で、時間を守るための行動をする」ことではないか・・ということです。どの程度早めにいくかは、その人の采配の結果であり、各人の任意です。例えば、「自分は仕事のスピードが遅く、定時では時間が足りない・・だから私は30分早く出社する」・・・という行為や、「早く行って、資料を読んでおきたい、だから早めに・・」というような行動が「自己采配」であり、優れた行動だと思います。そして、これは誰かに強制されるべきものではないと思います。一方、「私は2分前まで別の仕事をする、だから定刻の30秒前に席に着く」ことも、「5分遅れで参加します」と事前連絡し、その通り遅刻することも、また正だと思います。これらもまた時間厳守行動の一つと言えると考えます。くどくなりますが、「定刻は、あくまでも定められた時刻が定刻」であり、それをずらしたら、「時間厳守」という言葉が意味を失う・・・と私は考えます。皆さんは、「時間厳守」について、どう考えられるでしょうか。
始業時刻や終業時刻、ミーティングの開始時刻、顧客へのアポイント時刻、来客の予定時刻など、仕事においては、いつも「定刻」がつきまといます。仕事に限らず、起床時刻や登校時間、PTAの会合時間、デートの待ち合わせ時間など、普通の人なら、時間(時刻)をある程度守って生きているはずです。そして、その時刻には原則、「遅れないこと」が求められます。「時間に遅れても、全然平気でノープロブレム」という人は、大物の外タレでもないかぎ
 り、平穏には生きていけないでしょう。
り、平穏には生きていけないでしょう。そうなると、決まった時刻に、努力して「遅れない」ようにする・・というのが、普通の人の感覚であり、ましてや仕事であれば、当然のこととして遅れない工夫を多くの人がされているかと思います。具体策としては、「定刻よりも少し前に現地に着く、待機する。」ということが一般的でしょう。よく言われるのが、「5分前行動」などの言葉です。なかには、自分の時計をわざと5分早めている人もいます。5分どころか、20分も30分も前に入る人もいます。なるほど、これを実行すれば、定刻に「遅れる」ことはなくなります。約束の時間に遅れて、待たせた人(達)に文句を言われることもなくなるわけです。
では、これが、「時間厳守」の特効薬であり、これが時間管理の極意なのでしょうか。
たしかに、「時間より早め」は、「定刻に居る」ことには有効であり、その事自体に異論はありません。しかし、個人的には、この「早め、早め症候群」に異を唱えたくなるときがあります。一度立ち止まって、本来の時間厳守の「意味」を考えるべきだと思うのです。なぜ「時間厳守」なのか。それは、「ある約束事を、事前に決めた定刻通り始めることで効率的に時間を使い、決められた時間内で最大限の成果を上げる」・・という「目的」を達成する「手段」として、時間厳守の観念が存在していると言えないでしょうか。しかしながら、ともすると、この時間厳守や「早く着く」こと自体が無意識に「目的化」されてしまい、結果として、「早め、早め」が最も重要な目的であり、価値のあることのように勘違いされることが世の中では(とくに組織では)よくあるように思います。「早め」が目的になってしまうと、10分、20分、いや1時間でも2時間でも早く着くことが“優れた”ことのようにはき違え、そうしない人を非難する・・という、非常に奇妙な現象が起こる場合があります。その一方で、そこまでして「前倒し」して始めた仕事や会議の中身はさっぱり・・なんてこともあるように思います。
私自身は、時間に正確でありたいと思い、電波時計が発売された当初から腕時計はずっとこのタイプですが、昔、会議のきっかり3分前に会議室に入室したら、私以外は全員着座しており、上席者に「遅い!」となじられた経験があります。10数年も前の話ですが、今もってその考えは理解できませんし、承服できません。
○「定刻」とは、前でも後でもない
定刻とは、決められた時間、当事者同士が約束した時間ですよね。つまり、合意に基づいて決められた時刻の事を指します。交通機関であれば、電車やバス、飛行機やフェリーなど、すべて、「定刻」を元に動いています。 朝一便の出発時刻が「7:30」ということは、「7:30」に出発する・・ということが交通機関を運営する会社と利用者側との合意事項であり、これは、「7:00」でもなく、「7:40」でもありません。時間に正確であり、「時間厳守」というのは、この場合、「7:30」ジャストを指します。もし、電車が勝手に、「5分前行動」などといって、7:25に発車したら、利用者は怒るでしょうし、頻発すれば、大きな混乱を招き、危険ですらあります。かといって、7:40まで遅れるのも、非常に迷惑です。
私たちの身の回りではどうでしょうか。前記のように、「○時○分定刻」に対して、とかく「早め、早め」が無条件に美徳とされていないでしょうか?出社時間であれば、早く出勤すればするほど、会議であれば、早く会議室に行けば行くほど“偉い”かのような常識?があるようにも感じます。
しかし、果たして、そうでしょうか。もし、「決めた時間より早いほうが良いことがある」のであれば、一体何のために「定刻」を定めるのでしょうか。10分早いほうが絶対的にいいという根拠があるのであれば、定刻を10分早く設定し、その時間を厳守した方がいいと思います。巷で美徳とされがちな、「定刻より早め(の入室、入場、待機、あるいは開始)」とは、単に「決めた時間を、“前にずらす”」ということであり、「時間に対して不正確」といえないでしょうか。私は、7:30は、あくまで7:30が定刻であり、「早い方が偉い」というのは、根拠のない幻想だと思います。大事なのは、「7:30ジャストに、そこにいる(or行動を開始する)ことを守る。」であり、そして、「その仕事や活動の質を上げる」ことではないでしょうか。
こういうと、「時間前に、約束の場所に行くことは悪いことか」と反論される方もおられるかもしれませんが、そういう意味ではありません。私自身も、時間を守る場合は、おおむね5分前くらいには、現地にいることが多いです。その際に留意するのは、「時間を守る」ことであり、そのために事前に「どう行動するか」ということだけです。当然、「時間に遅れる」ことは、NGであり、当人のミスです。電車や飛行機と同様、遅れた人を待つ必要は全くありません。「遅れる」というミスを起こした場合は、そのリスクを自分で背負う必要があると思います。だからといって、何も考えず、必要以上に早め、早めに現地に行って、待ち時間をつくることは、時間の浪費だと思います。その時間は、多くの場合「非生産的」な時間になります。営業マンの例でいえば、あまり早く約束の時間より前に顧客を訪問することは、失礼な行為になると思います。個人的には、営業訪問の場合は、2分前くらいがちょうどよいのでは・・と思っています。
結論として申し上げたいのは、「時間厳守」、つまり「時間(定刻、定時)を守る」ということにおいて大事なのは、無策に早めに行くことではなく、「自分の采配で、時間を守るための行動をする」ことではないか・・ということです。どの程度早めにいくかは、その人の采配の結果であり、各人の任意です。例えば、「自分は仕事のスピードが遅く、定時では時間が足りない・・だから私は30分早く出社する」・・・という行為や、「早く行って、資料を読んでおきたい、だから早めに・・」というような行動が「自己采配」であり、優れた行動だと思います。そして、これは誰かに強制されるべきものではないと思います。一方、「私は2分前まで別の仕事をする、だから定刻の30秒前に席に着く」ことも、「5分遅れで参加します」と事前連絡し、その通り遅刻することも、また正だと思います。これらもまた時間厳守行動の一つと言えると考えます。くどくなりますが、「定刻は、あくまでも定められた時刻が定刻」であり、それをずらしたら、「時間厳守」という言葉が意味を失う・・・と私は考えます。皆さんは、「時間厳守」について、どう考えられるでしょうか。
カラオケ好き?
Posted by Even侍 at 22:47 2013年07月15日
私は、歌うことが割と好きです。車の中では、周りにわからないようにいつも歌っています。特に専門的な音楽の勉強などしたことがないので、無手勝流もいいところですし、まさにヘタの横好きってやつでしょうが、とにかく、歌うことは昔から好きでした。自分に音楽の才能がないからなおさらなのですが、ミュージシャンにはすごくあこがれます。もし、「生まれ変わったら何になりたいか。」と問われたら、迷うことなく「ミュージシャンになりたい。」と答えると思います(生まれ変わったとしても、”なれる”かどうかは別問題ですよね。^^;)。
歌うことが好きになったのは、自分が高校生くらいのころから流行り始めた、「カラオケボックス」の影響が大きいと思います。もっと昔の「カラオケ」とは、演歌中心であり、演歌好きのおじさんたちが大枚叩いて買う何十万もするセットか、飲み屋さんにあるあれ・・というイメージでしたが、カラオケボックスができたことにより、一気に一般化したように思います。思えば、最初のころの「カラオケボックス」って、ほんとに貨物のコンテナを「ボックス」として使ってましたね。今思うと、すごい発想です。
私も学生時代からカラオケには友人とよく行きましたし、社会人になってからもちょくちょく行ってました。というか、飲み会とカラオケ(ボックス)はセットみたいな時代がありましたよね。一次会からカラオケボックスなんてこともあったような・・。
何かのきっかけで、友達とNHKの「のど自慢」の予選に出ることになり、その友人は予選を見事通過しTVに出られたのに、私は見事落選した・・という笑うしかない思い出もあります。ちなみに、そのTVに出た友人は、私の家内です(笑)。
ここまで書くと、「お前、どんだけカラオケ好きやねん!」と思われるかもしれません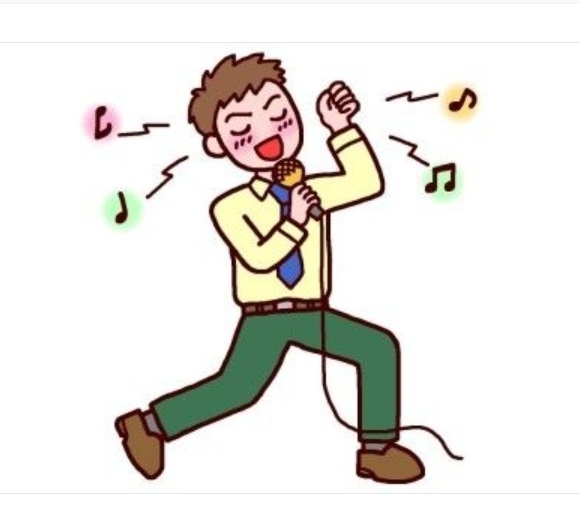 が、実は、私は、「カラオケ好き」という言葉にどうしても抵抗があり、「○○さんて、カラオケ好きだよねえ。」とはできたら言われたくない・・と思ってしまうのです。
が、実は、私は、「カラオケ好き」という言葉にどうしても抵抗があり、「○○さんて、カラオケ好きだよねえ。」とはできたら言われたくない・・と思ってしまうのです。
何故かといいますと、「カラオケ好き」のイメージは、時たま見かける、スナックなどで一人カウンターの隅に陣取り、延々と歌い続けるおっちゃん・・のイメージが、私の中では非常に強く、それがどうにも「かっこ悪く」思えてならないからです。まことに勝手なイメージとは知りながら、なぜかそのイメージが、「カラオケ好き」「カラオケで歌うことが好き」な人のイメージまで悪くしているような気がするからです(いや、ほんとに私の妄想かもしれませんが)。もちろん、スナックやバーで歌うカラオケはぜんぜんいいと思うのです。というより、私もさんざん友達や同僚と歌ってきました。もし、「二次会はカラオケのない、ピアノバーじゃなきゃだめだよね。」とかキッパリのたまわれても、肩をすくめると思います。
そうではなく、カウンターでひとりでも、グループの中のひとりであっても、「あー、あの人相当カラオケ好きなんやろなあー。で、相当自分がうまいって思ってるんやろなー。悦に入ってんなー。もう何曲目や。店の人も、横にいる人も、たぶん、嫌気がさしてるのに、全然気づいていないなー。」と思わせる、あの「カラオケ好き」な人、これがだめなんです。なぜかなあ、こういう人、どの店に言っても見かけるような。なぜかポマードのリーゼント系のおっちゃんが多いような・・。
まあ、もちろん何をどんな風に歌おうと、それは自由ですし、ほんとに人に迷惑をかけない限り、ダメなんていう権利がないこともわかっているんですけどね。
ですから、私はカラオケで歌うとき、ときたまフラッシュバックのように、「う!まさか今の俺は、あの”カラオケ好きさん”になっていないだろうか?」と、恐怖で一瞬背中がぞくっとすることがあります。そして、心の中で頭をブンブン横に振りながら、「みなさーん、私は、”うたが好き”であって、”カラオケ好き”ではありませんので、そこのところ、お間違えなきよう、よろしくお願いしまーす!」などとうったえながら、歌っている自分がいます(笑)。
うーむ、正直に気持ちを書いたのに、客観的に読むと、「いや、ほんとそれ、どっちでもいいし。」と思えるなあ。これを私の友人が見たら、「お前その割には”ウルトラソウル”えらい張り切って歌ってたよなあ。りっぱな”カラオケ好き”なんじゃねえの?」と突っ込まれそうです。(笑)
歌うことが好きになったのは、自分が高校生くらいのころから流行り始めた、「カラオケボックス」の影響が大きいと思います。もっと昔の「カラオケ」とは、演歌中心であり、演歌好きのおじさんたちが大枚叩いて買う何十万もするセットか、飲み屋さんにあるあれ・・というイメージでしたが、カラオケボックスができたことにより、一気に一般化したように思います。思えば、最初のころの「カラオケボックス」って、ほんとに貨物のコンテナを「ボックス」として使ってましたね。今思うと、すごい発想です。
私も学生時代からカラオケには友人とよく行きましたし、社会人になってからもちょくちょく行ってました。というか、飲み会とカラオケ(ボックス)はセットみたいな時代がありましたよね。一次会からカラオケボックスなんてこともあったような・・。
何かのきっかけで、友達とNHKの「のど自慢」の予選に出ることになり、その友人は予選を見事通過しTVに出られたのに、私は見事落選した・・という笑うしかない思い出もあります。ちなみに、そのTVに出た友人は、私の家内です(笑)。
ここまで書くと、「お前、どんだけカラオケ好きやねん!」と思われるかもしれません
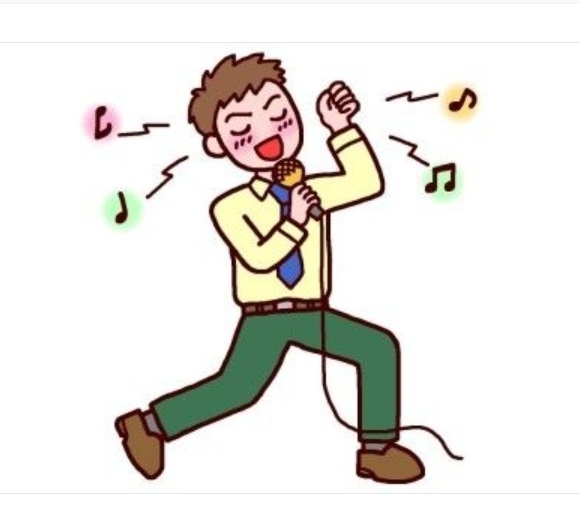 が、実は、私は、「カラオケ好き」という言葉にどうしても抵抗があり、「○○さんて、カラオケ好きだよねえ。」とはできたら言われたくない・・と思ってしまうのです。
が、実は、私は、「カラオケ好き」という言葉にどうしても抵抗があり、「○○さんて、カラオケ好きだよねえ。」とはできたら言われたくない・・と思ってしまうのです。何故かといいますと、「カラオケ好き」のイメージは、時たま見かける、スナックなどで一人カウンターの隅に陣取り、延々と歌い続けるおっちゃん・・のイメージが、私の中では非常に強く、それがどうにも「かっこ悪く」思えてならないからです。まことに勝手なイメージとは知りながら、なぜかそのイメージが、「カラオケ好き」「カラオケで歌うことが好き」な人のイメージまで悪くしているような気がするからです(いや、ほんとに私の妄想かもしれませんが)。もちろん、スナックやバーで歌うカラオケはぜんぜんいいと思うのです。というより、私もさんざん友達や同僚と歌ってきました。もし、「二次会はカラオケのない、ピアノバーじゃなきゃだめだよね。」とかキッパリのたまわれても、肩をすくめると思います。
そうではなく、カウンターでひとりでも、グループの中のひとりであっても、「あー、あの人相当カラオケ好きなんやろなあー。で、相当自分がうまいって思ってるんやろなー。悦に入ってんなー。もう何曲目や。店の人も、横にいる人も、たぶん、嫌気がさしてるのに、全然気づいていないなー。」と思わせる、あの「カラオケ好き」な人、これがだめなんです。なぜかなあ、こういう人、どの店に言っても見かけるような。なぜかポマードのリーゼント系のおっちゃんが多いような・・。
まあ、もちろん何をどんな風に歌おうと、それは自由ですし、ほんとに人に迷惑をかけない限り、ダメなんていう権利がないこともわかっているんですけどね。
ですから、私はカラオケで歌うとき、ときたまフラッシュバックのように、「う!まさか今の俺は、あの”カラオケ好きさん”になっていないだろうか?」と、恐怖で一瞬背中がぞくっとすることがあります。そして、心の中で頭をブンブン横に振りながら、「みなさーん、私は、”うたが好き”であって、”カラオケ好き”ではありませんので、そこのところ、お間違えなきよう、よろしくお願いしまーす!」などとうったえながら、歌っている自分がいます(笑)。
うーむ、正直に気持ちを書いたのに、客観的に読むと、「いや、ほんとそれ、どっちでもいいし。」と思えるなあ。これを私の友人が見たら、「お前その割には”ウルトラソウル”えらい張り切って歌ってたよなあ。りっぱな”カラオケ好き”なんじゃねえの?」と突っ込まれそうです。(笑)



